日蓮の『守護国家論』には、
「源空並びに所化の弟子、法華・真言等を以て雑行と立て難行道と疎み、行者をば群賊・悪衆・悪見の人等と罵り、或は祖父の履に類し〈聖光房の語〉、或は絃歌等にも劣ると云ふ〈南無房の語〉、其の意趣を尋ぬれば偏に時機不相応の義を存するが故なり。」(原漢文。御書システム№11209)
とあるが、これは法然とその門弟が「法華・真言等」、とりわけ法華経を雑行・難行道と下し、法然はその行者を群賊・悪衆・悪見等と罵り、弟子の聖光は法華経を祖父の履物の類い、智慶は詩歌管弦より劣ると蔑んでいる、との意味である。
ここに法然門下として、聖光と智慶が法華批判を展開したとあるが、隆寛弟子の南無房智慶については、拙稿「身延文庫蔵 日進本『浄土宗見聞・下』の翻刻並びに解題」にて解説したので、ここでは聖光房弁長(1162~1238)について述べてみたい。
聖光は、法然に師事して学ぶこと前後八年におよび、『選択集』を授与されるほどの高弟であった。九州に善導寺(浄土宗大本山)はじめ48箇寺を建立し、その門派を鎮西義、鎮西流と称した。付法の弟子良忠は日蓮批判の急先鋒となり、竜口法難や佐渡流罪の契機となる訴えを幕府に起こしている。
ところで『守護国家論』の〈聖光の語〉は、法華経を「祖父の履に類し」と記すのみで、今ひとつ意味が判然としないが、日進本『浄土宗見聞・下』には、
「又法然の弟子聖光は十巻の書を造る。第十巻は法然に値ふの時の昼の物語なり。此の書に云く、又上人、ある時の物語に云く、聖道門は喩えば祖父の沓のごとし。祖父大足のためにこれを用うと雖も、殊に小足のためには更に用に中らざるなり。当世の人は昔跡を追って聖道を修せんと欲する事、亦た復た是のごとし云云。道綽の意なり。あるいは又祖父の弓のごとし。」(原漢文。『日蓮仏教研究』第15号19頁参照)
と記されている。通釈してみよう。
法然のある時の物語に、聖道門(法華経)は喩えていえば、祖父の履が大足に適応しても、小足には役に立たないようなもの。今頃の人が昔の跡を追いかけて聖道門を修行することも同じである。これは浄土の祖師道綽の教えで、「祖父の弓」に喩える場合もある、等となろうか。つまり法華経は、上根を対象にしたもので、下根下機の衆生は救えないと非難している。
この日進本『浄土宗見聞・下』の大略は、日進と親交のあった日全『法華問答正義抄』「浄土宗釈」にも、
「五、法然已下の念仏者の謗証の事。
法然の弟子聖光、十巻の書を造る。第十巻には法然の口伝法門の相を書くなり。此の書に云く、上人、ある時物語に云く、聖道門は喩えば祖父の沓のごとし。祖父の大足のためにこれを用うと雖も、孫の小足のためには更に不用なり。当世の人は昔跡を追って聖道を修せんと欲する事は、また復たかくのごとし文。また随って堕す云云。」(原漢文。日蓮門下通用文献システム№106594)
と示されている。ここに聖光の「十巻の書」、「祖父の大足」、「当世の人……」など、『浄土宗見聞・下』と同様の記述が続くので、『法華問答正義抄』は日進の教示を受けたものと推察されよう。
もう一つ、啓運日澄の『嘉会宗義抄』にも次のような記述がみえる。
「二に選択に云く、諸行は機にあらず。時を失う。聖道の一種は証し難し。一には、法然の弟子に聖光、十巻の書を造る。此の書に云く、上人ある時の御物語に云く、聖道門は喩へば祖父大足の沓のごとし。孫足のために更に用に立たざるなり。あるいは亦祖父の弓のごとし。当世の人の昔跡を追うに似たり。是れ道綽の意なり。」(原漢文。日蓮門下通用文献システム№137949)
これは法然『選択集』の意を受けて、法華経・聖道門の諸行は機にあらず、時を失うと非難したもの。聖光の「十巻の書」以下は、『浄土宗見聞・下』『法華問答正義抄』と同意の文を綴っている。
ただし、日澄(1441~1510)は日進・日全より時代がかなり下るので、おそらく日澄が身延登詣の際に、『浄土宗見聞・下』(『金綱集』)等を参照し学んだものであろう。「道綽の意なり」まで同じなのは偶然の一致とも思えない。
また『浄土宗見聞・下』、『法華問答正義抄』、『嘉会正義抄』の三書はともに、浄土側の主張として、聖光の「十巻の書」により法華経・聖道門を「祖父の履」と下して非難するが、この元になったのは、了慧道光撰『拾遺漢語灯録』の以下の一文ではなかろうか。
又一時、師語って曰く、聖道門は之を喩えるに祖父の履の如し。祖父は大足なり。児孫は小足なり。其の履を用いべからざる也。今の人、昔賢の跡を追って聖道門を欲するも亦復是の如し。これ道綽禅師の意也。或文に祖父の弓の如しと。(原漢文。『浄土宗全書』9巻462頁。)
道光(1243~1330)は、法然の遺文・消息・法語を集成し、『黒谷上人語灯録』全18巻にまとめた人物で、聖光・良忠の跡を継いで、鎮西流が浄土宗の正統であることを主張した。『黒谷上人語灯録』は文永11年~12年の成立で、『漢語灯録』10巻、『和語灯録』5巻、『拾遺灯録』3巻(上中2巻は「漢語灯録」、下巻は「和語灯録」)から成っている。刊本が出版されたのも早く、元亨元年(1321)7月、道光79歳の時に上梓されている。
「祖父の足」の一段は、ほとんど日進本『浄土宗見聞・下』と同文である。おそらく日進は、『黒谷上人語灯録』の写本か刊本を所持し、その閲覧を果たしたのではなかろうか。
ひるがえって、日蓮遺文『守護国家論』は正嘉3年(1259)の成立とされるので、『黒谷上人語灯録』の記述とは関連しない。
ちなみに『守護国家論』には他にも、
「門弟此の書を伝へて日本六十余州に充満するが故に、門人世間無智の者に語りて云く、上人智恵第一の身と為りて此の書を造り真実の義と定め、法華・真言の門を閉ぢて後に開くの文無く、抛ちて後に還りて取るの文無し、等と立つる間、世間の道俗一同に頭を傾け、其の義を訪ふ者には仮字を以て選択の意を宣べ、或は法然上人の物語を書す間、法華・真言に於て難を付けて、或は去年の暦、祖父の履に譬へ、或は法華経を読むは管絃より劣ると。」(原漢文。御書システム№11390)
とあり、法然門下が『選択集』をもとに「法然上人の物語」を書いて、法華経を「祖父の履」に喩えたと記されている。
また、『戒体即身成仏義』にも、
或復顰蹙と云へるは、法華経を行ずるを見て、くちびるをすくめて、なにともなき事をする者かな。祖父が大なる足の履、小さき孫の足に協はざるが如くなんど云ふ者なり。(原漢文。御書システム№10142)
とあり、『唱法華題目抄』にも、
「何に況や、智恵第一の法然上人は、法華経等を行ずる者をば、祖父の履、或は群賊等にたとへられたりなんどいゐうとめ侍るは、是の如く申す師も弟子も、阿鼻の焔をや招かんずらんと申す。」(御書システム№12321)
との記述がみえるが、その系年は、『戒体即身成仏義』→宝治年間(1247~49)、『唱法華題目抄』→文応元年(1260)と推定される。いずれも日蓮初期の述作であれば、道光『黒谷上人語灯録』を典拠にしたものではない。
その記述も、日進本『浄土宗見聞・下』のように、「聖道門は喩えば祖父の沓のごとし。祖父大足のためにこれを用うと雖も、殊に小足のためには更に用に中らざるなり。当世の人は昔跡を追って聖道を修せんと欲する事、亦た復た是のごとし云云。道綽の意なり。」等と詳しく解説せず、至って簡略である。
すなわち、日蓮は他の浄土関係の文献によって、『守護国家論』に「祖父の履に類し〈聖光房の語〉」と記したわけで、日進は日蓮滅後にその典拠を道光『黒谷上人語灯録』に求めたことになろうか。
ただし、『黒谷上人語灯録』の当該部分の記述は、冒頭に「浄土随聞記第二 勢観上人著」と内題があり、道光は聖光の言葉として記していない。「勢観上人」とは法然の高弟源智(1183~1238)のことである。
ここには幾つか推測し得ることもあるが、長くなるので次の機会に譲りたい。(池田)
【参考図版】

身延文庫蔵 日進本『浄土宗見聞・下』。初行に「又法然弟子聖光造十巻書……」とみえる。当該部分の翻刻については、拙稿所収『日蓮仏教研究』第15号19頁参照。
※図版は無断転載禁止です。


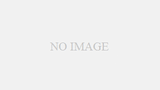
コメント